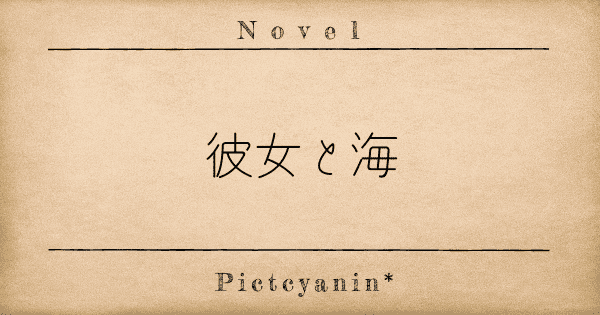身体にまとわりつく風が、これまでになかったものを運んできていると実感させる。

海、というものだそうだ。

行くあてもなく、ただ新しく出来た、それを眺めた。

戦争が終わり、機械の力を持った兵士には居場所はなくなくなった。
彼女も戦争で死んだ妹のためにと志願したが、
もしかしたらそれも植え付けられた偽の記憶かもしれない。
戦争で指揮を取っていたひとりが、洗脳をして自軍の兵士を増やし、機械化させた罪で戦後、死刑となっていた。
彼女の直属の上司であったが、別にそんなことはどうでもよかった。

今の自分に残されているのは、今在る世界には相応しくないであろう大きすぎる力と、
戦争によって新しく出来た「海」によってもたらされた、
「塩」というものにより、だんだんと朽ちていくであろうこの身体だけだ。

鈍色の空と、それに呼応するような暗い色の「海」を、彼女はただ見ていた。
この身体と共に、自分の魂も「塩」によって錆びて、朽ちていくのだと。

でも、それでよかった。
彼女にとって、兵器となったこの身体は不要であると、彼女自身が一番理解していたからだ。